フリーランスの方々が確定申告をするかどうかを判断するためには、いくつかの要素を考慮する必要があります。所得の有無や金額の範囲、他の所得があるかどうか、法人格を持っているかどうかなど、個々の状況によって確定申告の必要性が異なるからです。今回は、確定申告の必要有無の判断基準やそれに関連するケース、さらには確定申告の手順や必要な書類についても詳しく説明していきます。確定申告について詳しく知りたい方は、ぜひ読み進めてください。
1. 確定申告の必要有無

確定申告は、フリーランスや個人事業主などの所得者が年に一度行う税務手続きです。しかし、確定申告をする必要があるかどうかは、個々の状況によって異なります。以下では、確定申告の必要有無を判断するためのケースを見ていきましょう。
1.1 所得の有無
確定申告の最も基本的な要件は、所得の有無です。事業所得や不動産所得など、確定申告をする対象となる所得がある場合は、確定申告が必要です。所得の具体的な金額や種類によって、申告が必要かどうかが決まります。
1.2 所得金額の範囲
確定申告の必要性は、所得金額の範囲によっても異なります。一般的には、事業所得が年間で48万円を超える場合には、確定申告が必要とされています。ただし、この金額はあくまで目安であり、個別の所得状況によって異なる場合もあります。
1.3 他の所得がある場合
もしフリーランスの方が他の所得も得ている場合、例えばサラリーマンやアルバイトの給与など、その他の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要とされることがあります。この場合、複数の所得を合算して判断する必要があります。
1.4 法人格を持つ場合
もしフリーランスの方が法人格を持ち、法人として事業を行っている場合は、確定申告の対象は法人税となります。法人税の申告期限や手続きは個別の法人の種類や規模によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
1.5 持続的に事業を行う意思がある場合
確定申告の必要性は、将来的に事業を継続する意思があるかどうかでも変わります。一度確定申告を行った場合、税務署にとっては事業の実態や将来性を把握するための重要なデータとなります。そのため、将来的に事業を継続する意思がある場合は、確定申告を行うことが望ましいとされています。
以上が、確定申告の必要有無を判断するためのポイントです。次に、確定申告が必要なケースについて詳しく見ていきましょう。
2. 確定申告をしたほうがいいケース
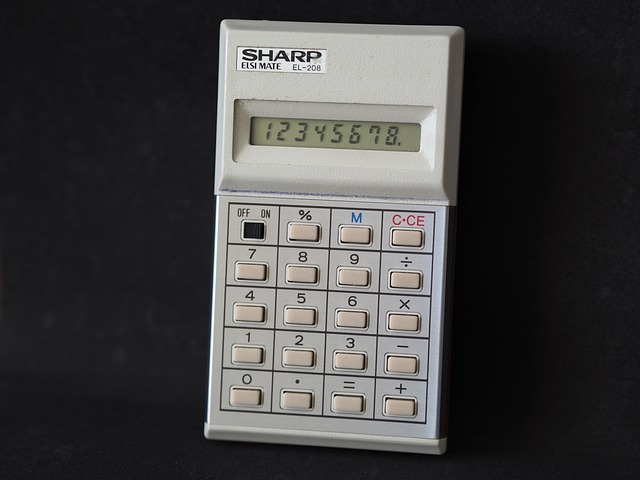
確定申告が不要なケースを前述しましたが、一方で確定申告をしたほうが得をするケースも存在します。以下に3つのケースを紹介します。
2-1. 赤字だった場合
フリーランスや自営業の人で、その年が赤字だった場合には原則的に確定申告は不要だと説明しました。しかし、赤字だった場合にもあえて確定申告を行うことでメリットがあります。
赤字を確定申告で申告すると、「純損失の繰越控除」という制度を利用することができます。これは、赤字額を最長3年間繰り越すことができる制度です。
純損失の繰越控除を利用することで、将来黒字化したときに過去の赤字と相殺し、課税所得を減らすことができます。つまり、赤字が出たら確定申告を行っておくことで、将来の課税所得を軽減させることができるのです。
また、赤字になった場合に確定申告をすると、税金の還付や住民税の軽減などのメリットもあります。ただし、純損失の繰越控除は、事業所得・不動産所得・山林所得から生じたものにしか適用されないので注意が必要です。
2-2. 源泉徴収されている場合
確定申告の対象者でなくても、源泉徴収された収入がある場合には確定申告を行ったほうが得をすることがあります。
源泉徴収は、支払い前に税金が差し引かれているため、払いすぎている可能性があります。しかし、源泉徴収を受けたまま確定申告をしないと、払いすぎた税金は戻ってきません。
確定申告をすることで正確な納税額を申告し、払いすぎた分の税金を還付してもらえます。特に、源泉徴収が行われている仕事があり、その情報が確定申告に反映される場合は、確定申告をすることをおすすめします。
2-3. 住民税の申告を別途やりたくない場合
確定申告が不要なケースでも、住民税の申告は別途行う必要があります。年末調整や確定申告を通じて納付するのは所得税であり、住民税ではありません。
確定申告を行った場合は、所得税を管轄する税務署から各自治体へ情報が届けられ、住民税の計算が行われます。一方、確定申告を行わなかった場合は、住民税の計算が行われません。
そのため、確定申告を行わなかった場合には、別途自分で各自治体へ住民税の申告を行う必要があります。もし住民税の申告を行わず、納付を怠った場合には罰則が課される可能性があります。
確定申告をあえて行うメリットがあり、いずれにしても住民税の申告は別途必要となることから、自分の状況に応じて確定申告を検討しましょう。
以下の表は確定申告の要・不要のケース別メリットをまとめたものです。
| ケース | メリット |
|---|---|
| 赤字だった場合 | 純損失の繰越控除、税金の還付、住民税の軽減 |
| 源泉徴収されている場合 | 払いすぎた税金の還付 |
| 住民税の申告を別途やりたくない場合 | 住民税の計算が自動的に行われる、住民税の申告手続きを省略できる |
上記のように、確定申告を行うことでメリットがあるケースが存在します。ただし、個々の状況によって異なるため、確定申告の必要性を自身の状況に合わせて慎重に判断しましょう。
3. 確定申告の手順STEP1: 所得を算出するデータを集める

確定申告を行うためには、まず所得を算出するためのデータを集める必要があります。以下に、所得を算出するために必要なデータとその集め方をまとめました。
データ集めの準備
まずは所得を算出するために必要なデータを整理しましょう。以下の項目を確認し、必要なデータを集めてください。
- 収入源の種類
-
給与所得、事業所得、不動産所得など、自分の収入源がどのカテゴリーに該当するかを確認してください。
-
収入の金額
-
各収入源ごとに、受け取った給与や売上などの金額を集計してください。
-
経費の明細
-
事業所得の場合、経費を計上することで所得を減らすことができます。経費の明細を集めてください。
-
控除に関わる情報
- 所得控除や特別控除の適用を受けるためには、該当する情報が必要です。例えば医療費控除や教育費控除に関する領収書などを集めましょう。
データの整理
データを集めたら、次に整理します。以下の方法でデータを整理してください。
- カテゴリーごとにデータをまとめる
-
収入源ごとにデータをまとめ、収入の種類ごとに集計してください。
-
経費の明細を確認する
-
経費の明細を確認し、どのカテゴリーに該当するかを判断してください。
-
控除に関わる情報を整理する
-
控除に関わる情報を整理し、必要な書類を確認してください。
-
データをまとめる
- 収入、経費、控除に関わる情報をまとめてください。これらのデータを元にして所得を算出します。
以上の手順を踏んでデータを集め、整理しておけば、確定申告の際もスムーズに進めることができます。
3. 確定申告の手順STEP2: 所得控除に関わる資料を集める

所得控除を適用するためには、必要な資料を集める必要があります。以下に、確定申告に関わる所得控除の資料をまとめました。
1. 医療費控除
- 医療費控除を受けるための領収書や診療報酬明細書などの医療費関連の資料を集めます。
2. 教育費控除
- 教育費控除を受けるための経費明細書や領収書、学校からの支払明細書などの資料を集めます。
3. 住宅ローン控除
- 住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローンの利息明細書などの資料を集めます。
4. 寄付金控除
- 寄付金控除を受けるためには、寄付金領収書や寄付先への振込明細書などの資料を集めます。
5. その他の控除
- 所得控除に関わるその他の資料も必要に応じて集めます。具体的な資料は、該当する控除によって異なります。
これらの資料を集める際には、日付や金額、支払先などが明記されたものを選び、必要な数を確保しておきましょう。所得控除を適用するためには、正確な資料が必要となるため、注意して集めるようにしてください。
Use the following template table with the columns ‘所得控除の種類’, ‘必要な資料’, and ‘集める方法 to illustrate the necessary documents for each income deduction, and how to collect them:
| 所得控除の種類 | 必要な資料 | 集める方法 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 領収書、診療報酬明細書など | 医療機関からもらう |
| 教育費控除 | 経費明細書、領収書、学校からの支払明細書など | 学校や教育機関からもらう |
| 住宅ローン控除 | 住宅ローンの利息明細書など | 金融機関からもらう |
| 寄付金控除 | 寄付金領収書、振込明細書など | 寄付先や金融機関からもらう |
| その他の控除 | 該当する資料 | 購入先や関係機関からもらう |
所得控除に関わる資料を集める際には、必要な資料を的確に集めることが重要です。あらかじめ集める資料の種類や集める方法を把握しておき、スムーズに手続きを進めましょう。
4. 確定申告の手順STEP2: 所得控除に関わる資料を集める
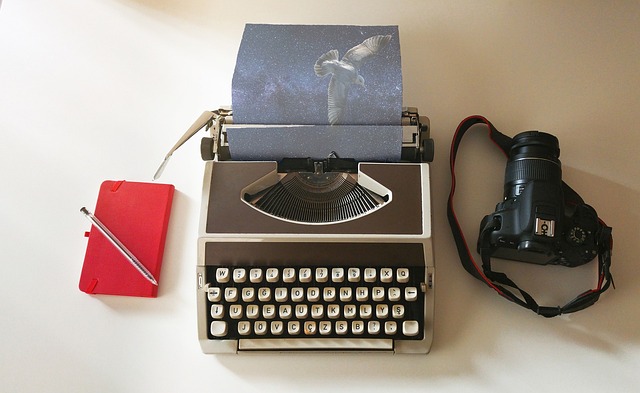
確定申告を行う際には、所得控除に関わる資料を正確に集める必要があります。所得控除は確定申告において重要な要素であり、適用される控除額によって税金の額が大きく変わるため、注意が必要です。
以下は確定申告の手順STEP2で行うべき所得控除に関わる資料の一部です。
4.1 社会保険料控除
社会保険料控除を受けるためには、社会保険料控除証明書の提出が必要です。この証明書は社会保険料の支払い実績を証明するものであり、雇用主や社会保険加入先から提供されます。確定申告の際には、社会保険料控除証明書の写しを準備しましょう。
4.2 医療費控除
医療費控除を受けるためには、医療費の明細書が必要です。医療費とは、診療費や薬局での薬代、歯科治療費、眼鏡やコンタクトレンズの費用などが該当します。これらの費用に関する明細書を集め、確定申告の際に提出しましょう。
4.3 生命保険料控除
生命保険料控除を受けるためには、生命保険料控除証明書の提出が必要です。この証明書は生命保険の支払い実績を証明するものであり、保険会社から提供されます。確定申告の際には、生命保険料控除証明書の写しを準備しましょう。
4.4 地震保険料控除
地震保険料控除を受けるためには、地震保険料等の控除証明書の提出が必要です。この証明書は地震保険料の支払い実績を証明するものであり、保険会社から提供されます。確定申告の際には、地震保険料等の控除証明書の写しを準備しましょう。
4.5 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除を受けるためには、掛金額払込証明書および小規模企業共済掛金払込証明書の提出が必要です。これらの証明書は企業共済の支払い実績を証明するものであり、共済団体から提供されます。確定申告の際には、掛金額払込証明書および小規模企業共済掛金払込証明書の写しを準備しましょう。
4.6 住宅ローン控除
住宅ローン控除を受けるためには、住宅借入金等特別控除額の計算明細書や住民票の写し、建物や土地の登記事項証明書、建物や土地の不動産売買契約書の写し、金融機関の住宅ローンの残高証明書などの提出が必要です。これらの資料は住宅ローンに関する情報や支払い実績を証明するものであり、それぞれの関係機関から提供されます。確定申告の際には、必要な資料を集めましょう。
以上が確定申告において所得控除に関わる資料の一部です。これらの資料を正確に集め、確定申告書に添付することで、適用される所得控除額を最大限に引き出すことができます。なお、詳細な所得控除の種類や必要な証明書については、関係する機関や税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページを参考にしてください。
5. 確定申告が必要か判断する手順

確定申告が必要かどうかを判断するためには、以下の手順を踏むことが重要です。
手順1: 所得税の基準額を確認する
まず、所得税の基準額を確認しましょう。所得税の基準額とは、その年度の収入に対して所得税を納める必要がある金額のことです。基準額は、個人が得た年収や給与所得、事業所得、不動産所得などによって異なります。所得税の基準額は、税務署のホームページや税務署で確認することができます。
手順2: 控除や特別控除の適用を確認する
次に、所得税の基準額から控除や特別控除を適用することができるかを確認しましょう。控除や特別控除とは、所得税の納付額を軽減するための手続きです。例えば、住宅ローンの控除や扶養家族の控除などがあります。
手順3: その他の所得による影響を確認する
さらに、その他の所得によって確定申告が必要になる場合があります。例えば、株式や不動産の売買による所得や海外での収入など、多様な所得がある場合には確定申告が必要になることがあります。これらの所得は、別途申告する必要があります。
以上の手順を踏んで確定申告が必要かどうかを判断しましょう。確定申告が必要と判断された場合は、期限内に必要な書類を揃え、申告手続きを行ってください。
5. 確定申告が必要か判断する手順

確定申告が必要かどうかを判断するためには、以下の手順を踏むことが重要です。
- 所得税の基準額を確認する
- 所得税の基準額は、年収や給与所得、事業所得、不動産所得などによって異なります。
-
税務署のホームページや税務署で確認することができます。
-
控除や特別控除の適用を確認する
-
住宅ローンの控除や扶養家族の控除など、控除や特別控除が適用される場合は確認しておきましょう。
-
その他の所得による影響を確認する
- 株式や不動産の売買による所得や海外での収入など、その他の所得によっても確定申告が必要になることがあります。
以上の手順を踏んで確定申告が必要かどうかを判断しましょう。確定申告が必要と判断された場合は、期限内に必要な書類を揃え、申告手続きを行ってください。
6.確定申告書や必要な計算書等の作成手順

確定申告をするには、確定申告書や必要な計算書などを作成する必要があります。以下では、作成手順について詳しく解説します。
6.1.確定申告書の作成方法
確定申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。フリーランスの方は「確定申告書B」を使用します。まず、確定申告書Bをダウンロードしましょう。
次に、確定申告書Bの記入方法について説明します。確定申告書Bには、給与所得、公的年金、事業所得、不動産所得、配当所得、利子所得などの申告項目があります。自分が該当する所得項目の金額を正確に記入しましょう。
6.2.青色申告決算書の作成方法
青色申告を行う場合には、青色申告決算書の提出が必要です。青色申告決算書は、損益計算書とその内訳、貸借対照表を記載する書類です。一般用様式を使用します。
青色申告決算書の作成方法については、以下の手順を参考にしてください。
-
損益計算書の作成:自分の事業の収入と経費を明細にまとめます。収入から経費を差し引いた金額が事業所得となります。
-
貸借対照表の作成:自分の事業の資産と負債、純資産を明細にまとめます。資産から負債を差し引いた金額が純資産となります。
青色申告決算書は、クラウド会計ソフトなどを使用すると自動的に作成されることもありますので、活用してみてください。
6.3.収支内訳書の作成方法
白色申告を行う場合には、収支内訳書の提出が必要です。一般用用紙を使用します。
収支内訳書の作成方法については、以下の手順を参考にしてください。
-
収入の詳細を記入する:自分の事業における収入の詳細を記入します。主な収入源や金額を明確に記入しましょう。
-
経費の詳細を記入する:自分の事業における経費の詳細を記入します。主な経費項目や金額を明確に記入しましょう。
-
利益の計算:収入から経費を差し引いた額が所得金額となります。この金額を計算し、収支内訳書に記入しましょう。
収支内訳書も、クラウド会計ソフトなどを使用すると自動的に作成されることもありますので、便利に活用してください。
6.4.控除証明書の準備
確定申告には、控除証明書を準備する必要があります。控除証明書は、所得税の控除を受けるために提出する必要があります。以下は、主な控除証明書とそれに必要な書類の一覧です。
| 控除の種類 | 必要な証明書 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 社会保険料控除証明書 |
| 医療費控除 | 医療費の明細書 |
| 生命保険料控除 | 生命保険控除証明書 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料等の控除証明書 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | ・掛金額払込証明書 |
| ・小規模企業共済掛金払込証明書 | |
| 住宅ローン控除 | ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |
| ・住民票の写し | |
| ・建物、土地の登記事項証明書 | |
| ・建物、土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し | |
| ・金融機関の住宅ローンの残高証明書(控除初年度) |
控除証明書は、それぞれの控除に該当する書類を準備し、確定申告時に提出する必要があります。控除を受けるためには、正確な証明書の準備が重要です。
以上が、確定申告書や必要な計算書の作成手順になります。正確に作成し、提出期間内に確定申告を行いましょう。
まとめ
確定申告はフリーランスや個人事業主などの所得者が年に一度行う税務手続きです。確定申告の必要有無を判断するためには、所得の有無や金額の範囲、他の所得の有無、法人格の有無など個々の状況によって異なる要素を考慮する必要があります。
確定申告の必要性を判断するために、所得の有無や金額の範囲を確認しましょう。また、他の所得がある場合や法人格を持っている場合も、確定申告の必要性が生じることがあります。
一方で、確定申告をすることでメリットが生じるケースも存在します。赤字だった場合には純損失の繰越控除や税金の還付、源泉徴収された収入がある場合には払いすぎた税金の還付などのメリットがあります。
確定申告の手続きでは、所得控除に関わる資料を集める必要があります。控除に関わる資料を正確に集めることで、適用される控除額を最大限に引き出すことができます。
確定申告が必要かどうかを判断するためには、所得税の基準額の確認や控除の適用の有無を確認する必要があります。加えて、その他の所得による影響も考慮することが重要です。
確定申告をする際には、確定申告書や必要な計算書などの作成を行う必要があります。正確に作成し、期限内に提出することが大切です。
確定申告について詳しく知りたい方は、国税庁のホームページや税務署での相談などを活用してください。適切な手続きを行うことで、スムーズに確定申告を行うことができます。ぜひ、確定申告に関する情報をしっかりと理解し、的確な手続きを行いましょう。


