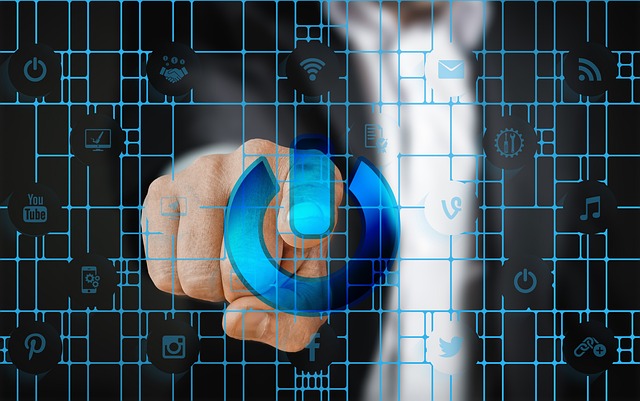フリーランスは独立して働くことで自由なスケジュールや収入を得ることができますが、その一方で税金の知識や申告・納付の手続きを自分で行う必要があります。所得税や住民税、消費税、個人事業税、国民健康保険料など、様々な税金が存在し、それぞれの計算方法や納付方法も異なります。フリーランスとして働く上で税金に関する正確な知識を持つことは非常に重要です。この記事では、フリーランスが把握しておくべき税金について詳しく解説します。
所得税

所得税は、フリーランスにとって重要な税金です。所得税は、収入から経費と所得控除を差し引いた金額に対して一定の税率をかけて課税されます。フリーランスは、毎年確定申告を行い、自分で税金の申告と納付を行う必要があります。
所得税の計算方法は、国税庁が公開している「所得税の速算表」を利用すると簡単に求めることができます。また、所得控除には基礎控除のほかに13種類の所得控除があります。これらの所得控除を利用することで、納税額を軽減することができます。
また、フリーランスはフリーランスの場合は、報酬から源泉徴収税が差し引かれている場合もありますが、そのすべてが源泉徴収されるわけではありません。したがって、年に一度自分で確定申告を行い、所得税の申告と納付を行う必要があります。
-
復興特別所得税
復興特別所得税は、平成25年から令和19年までの間に徴収される税金です。この税金は、東日本大震災からの復興財源を確保するために導入されたもので、所得税と一緒に計算・徴収されます。復興特別所得税は、前述の計算で算出した基準所得税額の2.1%となります。 -
住民税
住民税は、地域の公共サービス維持のために、すべての住民が負担する税金です。所得税と同じく、所得が多ければ多いほど負担が増える仕組みです。住民税は、「均等割」と「所得割」の2つの方法で計算されます。
均等割は、収入に関わらず定額の税金を納めるものであり、一般的には都道府県税1,000円と市区町村税3,000円の合計4,000円です。ただし、2014年から2023年までの間は防災費用確保のために、この税金が引き上げられています。
所得割は、前年の所得に対して一定の割合で計算されます。課税所得から所得控除を差し引いた金額に10%をかけて計算されます。所得税との違いは、所得控除の控除額が異なることです。注意が必要ですが、所得税が0円でも住民税は発生することがあります。
- 消費税
消費税は、商品やサービスの取引に課される税金です。フリーランスは、一定以上の年収があれば事業者として、消費税の申告と納税を行う必要があります。消費税の納税対象事業者になるためには、2年前の課税売上高が1,000万円を超えているか、1年前の課税売上高もしくは給与の合計が1,000万円を超えているか、または「消費税課税事業者選択届出書」を提出している必要があります。
消費税の計算方法は、事業者が預かる消費税は、軽減税率対象品は8%、その他は10%となります。消費税の納付方法は、確定申告を行った後に、所轄税務署に申告と納付を行います。納付希望金額が48万円を超える場合は、中間申告と納付が必要です。
- 個人事業税
個人事業税は、事業を営む個人が都道府県に納める地方税です。年間の所得が290万円を超える場合に納付義務が発生します。個人事業税の対象業種は70業種あり、業種ごとに税率が設定されています。計算方法は複雑ですが、確定申告を行い各自治体が計算を行います。
以上が、フリーランスが知っておくべき税金についての情報です。税金は個人の収入や所得に応じて計算・納付されるため、正確な情報を把握しておくことが重要です。確定申告の期限や納付期限に注意し、適切に申告・納税を行いましょう。
住民税

住民税は、地方税の一つであり、地域の公共サービスを維持するために住民全員が負担しています。所得税と同じく、収入が多ければ多いほど負担額も増える仕組みです。
住民税には、「都道府県民税」と「市区町村民税」という2つの内訳がありますが、合算して住民税として請求されます。
住民税は、均等割と所得割の2つの税率で計算されます。
均等割は収入に関わらず一律の金額が課されます。基本的には都道府県税1,000円と市区町村税3,000円の合計4,000円ですが、2014年度から2023年度までは防災費用確保のために都道府県税と市町村税がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。
所得割は、前年の所得に一定の割合を掛けて計算されます。所得税と似たような計算方法ですが、住民税のための所得控除の控除額は異なるため、注意が必要です。
所得割の税率は累進制で、所得が高いほど税率も高くなります。具体的な税率は国税庁のホームページなどで確認することができます。
また、所得税とは異なり、所得控除を利用しても住民税の納税額が0円にならない場合がありますので、注意が必要です。
住民税の支払いに困難がある場合は、各自治体で支払い猶予・減免制度が用意されていますので、窓口で相談してみましょう。
住民税の納付方法は、会社員の場合は給与天引きで特別徴収されます。一方、フリーランスや個人事業主の場合は、市町村から送られてくる納付書に基づいて納めることになります。
納付書には確定申告の内容を基に計算された住民税が記載されており、金融機関やコンビニエンスストア、口座振替などで支払うことができます。一部の自治体ではクレジットカード払いにも対応していますので、確認してみましょう。
確定申告をしていない場合は、自分で住所を管轄する自治体へ申告することが必要です。申告期限は原則として毎年3月15日ですので、忘れないようにしましょう。
住民税は日本の国民にとって重要な税金です。正確に計算し、適切に納付することが大切です。
消費税

3. 消費税
消費税は、商品やサービスの取引に課税される税金です。消費税には国税の消費税と地方消費税があります。消費税は消費者が払った税金を「事業者」が納めるという特徴があります。フリーランスも一定以上の年収があれば事業者として、年1回申告・納税を行う必要があります。
消費税の納税対象事業者(課税事業者)となる条件は以下の通りです。
- 2年前の課税売上高が1,000万円を超えている場合。
- 1年前の1月1日から6月30日までの課税売上高もしくは給与の合計が1,000万円を超えている場合。
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合。
また、フリーランスが免税対象となる場合でも、あえて消費税を納めることができる「消費税課税事業者選択届出書」を提出することでメリットを享受することができます。仕入れなどで支払った消費税が、消費者から預かった消費税よりも多い場合には還付を受けることができます。
消費税の計算方法は以下の通りです。
- 軽減税率対象品(酒類・外食を除く飲食料品、定期購読契約する週2回以上発行の新聞)は8%、その他は10%となります。
- フリーランスが預かった消費者からの消費税は、フリーランスが支払う仕入れに関する消費税と同じです。
フリーランスが実際に納める消費税の計算方法には、「本則課税」と「簡易課税方式」の2種類があります。
「本則課税」は、課税期間中の課税売上にかかる消費税と、課税期間中の課税仕入れにかかる消費税の差額を計算する方法です。
一方、「簡易課税方式」は、事業者の消費税計算を簡略にするための制度です。業種ごとに定められた「みなし仕入率」を課税売上に掛けて消費税額を計算します。ただし、簡易課税方式を利用できるのは、事前届出を行った課税売上高が5,000万円以下の事業主です。
地方消費税は、消費税を求めた後に地方消費税率(78分の22)を掛けて求めます。
なお、2023年10月からは課税事業者を対象に「インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)」が導入されます。従来は「売上と一緒に預かった消費税」から「仕入れで払った消費税」を控除して、その差額を納税していましたが、インボイス制度では「適格請求書(インボイス)」を発行してもらう必要があります。フリーランスは自身や取引先の状況やインボイス制度の導入についても考慮しながら、納税に対応する必要があります。
消費税の納付方法は、フリーランスや個人事業者は翌年の3月末日までに、算出した消費税と地方消費税を所轄税務署に申告・納付します。還付を受けたい場合は、還付申告書とその明細を提出する必要があります。中間申告・納付の必要がある場合も注意が必要です。
個人事業税

個人事業税は、フリーランスや個人事業者が都道府県に納める地方税の一つです。年間の所得が290万円を超える場合に納付義務が発生します。個人事業税の税率は業種によって異なり、3〜5%の範囲内で決まります。
法定業種に該当しない仕事(文筆業や芸能人、スポーツ選手、画家など)は、個人事業税の対象ではありません。しかし、エンジニアやWebライター、プログラマーなどは、仕事内容や契約内容によって請負業に分類されることがあります。その場合は、個人事業税の納付義務が生じるので注意が必要です。
個人事業税は、確定申告を基に各自治体が計算し、金額が決まります。計算方法は次の通りです。
(年間所得 + 所得税の事業専従者給与控除額 - 個人の事業税の事業専従者給与控除額 + 青色申告特別控除額 - 各種控除額) × 税率 = 個人事業税額
また、個人事業税は経費にすることができますので、確定申告の際には忘れずに計上しましょう。
個人事業税の納付方法は、毎年8月頃に届く納付書に従って一括もしくは年2回の分納で支払います。支払いは自治体窓口のほか、口座振替やコンビニエンスストア、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリ、金融機関のATMなどで行うことができます。
個人事業税は、フリーランスや個人事業者が納める必要がある税金です。確定申告の際には注意して計算し、納付方法も確認しておきましょう。
国民健康保険料
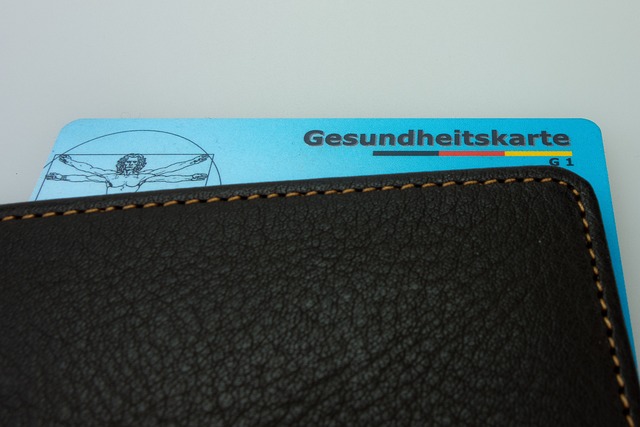
国民健康保険は、フリーランスや個人事業主などが加入する公的医療保険制度です。前述したように、国民健康保険は会社員が加入する健康保険とは異なり、全額が個人負担となります。
国民健康保険料の計算は、加入者の前年度の所得や世帯の加入人数、各自治体によって定められた料率に基づいて行われます。また、地域ごとの所得や医療水準などを加味して保険料が異なるため、保険料に地域差があることも特徴です。
会社員が加入する健康保険の保険料は、会社と折半して負担しますが、フリーランスなどが加入する国民健康保険の場合は、全額が個人負担となります。そのため、一般的には同じ年収でも会社員と比べて割高になる傾向があります。
具体的な国民健康保険料の額は、各自治体の窓口で試算してもらうことができます。窓口での相談や試算を利用することで、自分にとって最適な保険料のプランを見つけることができます。
また、国民健康保険料とは別に、介護保険料も納める必要があります。国民健康保険料と合わせて徴収される介護保険料は、40歳以上64歳以下の国民が対象であり、住んでいる市区町村によって異なる金額となります。詳細な料金は、各自治体のホームページなどで確認することができます。
国民健康保険料や介護保険料は、毎年6月に1年分の保険料の納付書が自宅に郵送されます。納付書払いか口座振替の選択があり、自治体によってはモバイルレジ納付やクレジットカード決済、電子マネー決済などの方法も利用できます。
国民健康保険料を納めることは、自身の健康を守るために重要な手続きです。具体的な金額や納付方法を確認し、適切に納付していきましょう。
まとめ
フリーランスとして働く際には、さまざまな税金についての正確な知識を持つことが重要です。所得税や復興特別所得税、住民税、消費税、個人事業税、国民健康保険料など、それぞれの税金には計算方法や納付方法があります。確定申告の期限や納付期限には注意し、適切に申告・納税を行いましょう。税金は個人の収入や所得に応じて計算・納付されるため、正確な情報を把握しておくことが重要です。フリーランスとしての活動がさらに円滑に進むよう、税金に関する知識をしっかりと持ちましょう。