個人事業主やフリーランスの皆さん、確定申告の時期が近づいてきましたね。確定申告は税金を正しく納めるために非常に重要な手続きですが、初めての方や手続きが分からない方も多いのではないでしょうか。今回は、「個人事業主の確定申告」をテーマに、確定申告の意味から、個人事業主が確定申告を行う必要性や方法について解説していきます。ぜひお役立ていただければ幸いです。
1. 確定申告とは

確定申告とは、毎年の所得にかかる税金額を計算し、税務署に申告書や必要書類を提出して納税する手続きです。この制度は、課税される収入を持つ人々が適正な税金を納めるために設けられています。
確定申告の対象となるのは、主に個人事業主やフリーランスなどの個人収入を得ている人々です。確定申告の必要性は、以下の2つの条件で判断されます:
- 年間の所得が一定額以上ある場合:一般的には年間の所得が少なくとも48万円以上ある場合に確定申告が必要です。
- その他の所得がある場合:副業やアルバイト、不動産収入などの給与以外の所得が年間20万円以上ある場合にも確定申告が必要です。
ただし、所得税には基礎控除という制度があり、この控除額を差し引いた所得がゼロ以下の場合は確定申告が不要となります。また、青色申告を行えば3年間分の赤字を繰り越せるため、課税所得がゼロ以下でも確定申告をしておくことがおすすめです。
確定申告の必要な人と不要な人の違いをまとめると:
- 確定申告が必要な人:年間の所得が一定額以上ある人、またはその他の所得が年間20万円以上ある人
- 確定申告が不要な人:所得税の基礎控除を差し引いた所得がゼロ以下の人
確定申告は個人事業主にとって重要な手続きです。次のセクションでは、個人事業主が確定申告をするべきかについて詳しく解説していきます。
2. 個人事業主が確定申告をすべきか
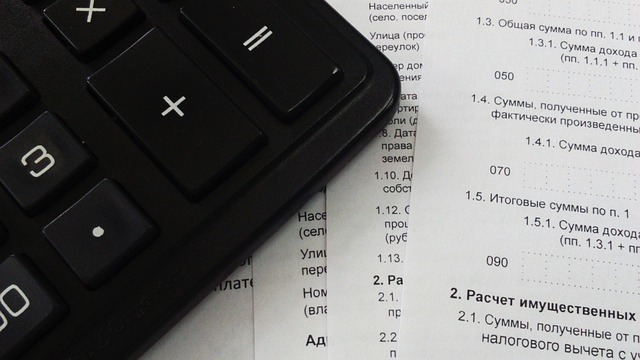
個人事業主として開業する際、確定申告についてどうすべきか気になる方も多いでしょう。しかし、個人事業主が必ずしも確定申告をしなければならないわけではありません。個人事業主の皆さんは、今後事業を営む上で、確定申告に対する正しい理解が必要不可欠です。
2.1 確定申告の必要性を判断するために
個人事業主が確定申告をする必要性を判断するためには以下のポイントを考慮すると良いでしょう。
- 経理作業を行うことによって本業に影響が出ない場合は、自分で確定申告を行うことができます。
- 不安がある場合や本業への影響が出そうな場合は、税理士に相談することをおすすめします。
2.2 確定申告を自分で行う場合の手続き
確定申告を自分で行う場合でも、確定申告ソフトを活用することで手続きを簡単にすることができます。特におすすめなのが、「やよいの青色申告オンライン」というソフトです。このソフトを使えば、簿記や会計の知識がなくても簡単に入力ができます。
以下は確定申告を自分で行う場合の手続きのシンプルな流れです。
1. 確定申告ソフトをダウンロードまたはアクセスします。
2. 必要な情報を入力します。例えば、所得や経費の詳細などです。
3. 入力が完了したら、確定申告書を作成します。
4. 作成した書類を提出します。
2.3 確定申告のリスクを理解する
確定申告を怠ると、以下のようなリスクが生じます。
- 無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
- 確定申告をしない場合は青色申告の特別控除を受けることができません。
これらのリスクを十分に理解した上で、確定申告を適切に行うようにしましょう。
2.4 所得による確定申告の必要性
個人事業主の場合、所得が48万円以下の場合は確定申告は不要です。なぜなら、基礎控除により所得が48万円以下の場合は課税所得が0円になるからです。そのため、所得税は発生せず、確定申告も必要ありません。
以上が個人事業主が確定申告をすべきかどうかを判断するためのポイントです。個人事業主の皆さんは、自身の状況に合わせて、上記の内容を参考にして判断を行ってください。確定申告に関する詳しい手続きや注意点については、後続のセクションでも解説します。
3. 経費にできるもの

以下に、個人事業主や自営業者が経費として計上できる具体的な項目をリストアップします。
3.1 租税公課
- 事業税
- 固定資産税
- 自動車税など
3.2 荷造運賃
- 商品の配送費用や梱包費用
3.3 水道光熱費
- 水道料金
- 電気料金
- ガス料金など
3.4 旅費交通費
- 飛行機代
- 電車賃
- 宿泊費など
3.5 通信費
- インターネット料金
- 電話料金
- 切手代など
3.6 広告宣伝費
- Web広告
- チラシ作成
- 看板など
3.7 接待交際費
- 取引先との飲食
- お歳暮の費用など
3.8 会議費
- 取引先との打ち合わせ時の飲食
- 会議室利用費など
3.9 消耗品費
- 文具
- 日用品
- ガソリン代など
3.10 減価償却費
- 車
- パソコン
- コピー機など
3.11 外注工賃
- 他社やフリーランスへの委託など
3.12 地代家賃
- 事務所の賃貸料
- 店舗使用料など
3.13 支払手数料
- 振込手数料
- 専門家報酬など
3.14 雑費
- クリーニング代など、他の経費に該当しないもの
これらの項目は、事業に必要な費用や売上に直接関わる支出です。経費として計上するためには条件があります。例えば、耐用年数が1年以上または取得額が10万円以上の固定資産は固定資産として申告できますが、その逆の場合は経費として申告することができます。経費の計上には上限はありませんが、適切な金額と頻度で計上することが重要です。
経費を正確に管理し、確定申告において得られる節税メリットを最大限に活用しましょう。
4. 確定申告の方法

確定申告の方法は様々です。以下では、主な確定申告の方法について解説していきます。
手書きで作成する
確定申告の用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。手書きで作成する場合は、用紙に必要事項を記入するだけです。手書きで作成する方法は、パソコンやネットを使うのが苦手な人に適しています。
ソフトを使って作成する
確定申告ソフトを利用すれば、作業時間を短縮することができます。パソコンに慣れている方は、確定申告ソフトを使うことをおすすめします。クラウド型とインストール型の2種類のソフトがありますが、ネット環境が整っている場合はクラウド型が便利です。ソフトを使えば、簿記の知識がなくても簡単に確定申告書を作成できます。
国税庁のWebサイトで作成する
国税庁のWebサイトには、確定申告書等作成コーナーがあります。ここでは、簡単な項目を入力するだけで確定申告書を作成できます。入力例や操作方法に関する質問も解説されているため、困った時に参考になります。国税庁のWebサイトで作成する方法は、一人で進めることができるため、手間を省きたい方におすすめです。
税理士に依頼する
確定申告が初めてで不安がある場合や、忙しくて時間が取れない場合は、税理士に依頼する方法もあります。税理士に確定申告書を作成してもらえば、経費や控除額の計算などを任せることができます。ただし、税理士に依頼する場合は、一定の費用がかかることを覚えておきましょう。
以上が、主な確定申告の方法です。自分に合った方法を選び、確定申告をスムーズに行いましょう。確定申告は時間をかけて慎重に行う必要がありますので、早めに準備を始めることをおすすめします。
5. 青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告は、確定申告の2つの制度であり、それぞれに特徴やメリットが存在します。以下では、青色申告と白色申告の主な違いについて説明します。
青色申告の特徴
青色申告は、税務署の承認を受けた個人事業主に対して優遇措置が適用される制度です。青色申告を行うためには、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告の特徴は以下の通りです:
– 税制上の優遇を受けることができます。青色申告特別控除を受けることができます。
– 3年間の赤字繰越が可能です。
– 貸倒引当金を損金として算入できます。
白色申告の特徴
一方、白色申告は青色申告に比べて手続きや帳簿の作成が簡潔な制度です。青色申告を選択しない個人事業主は自動的に白色申告となります。
白色申告の特徴は以下の通りです:
– 帳簿の作成方法がシンプルです。
– 青色申告のような節税メリットはありません。
青色申告と白色申告の適用条件
青色申告には特定の所得の内容や必要書類の提出が求められます。以下の条件を満たす個人事業主が青色申告に向いています:
– 事業所得、山林所得、不動産所得のいずれかの所得がある。
– 青色申告承認申請書を提出している。
– 青色申告決算書の提出が可能です。
白色申告はこれらの条件を満たさない個人事業主に向いています。
以上が青色申告と白色申告の主な違いです。個人事業主は自身の所得の内容や手続きの煩雑さなどを考慮して、適切な申告方法を選択することが重要です。
まとめ
個人事業主の皆さん、確定申告は重要な手続きです。自身の所得や事業の状況に合わせて、必要性を判断しましょう。確定申告が必要な場合は、経費の計上や確定申告書の作成など、手続きを適切に行うことが大切です。また、青色申告と白色申告に関しては、各々の特徴や適用条件を理解し、自身に最適な申告方法を選びましょう。確定申告は節税や個人事業主としての取引先などとの信頼構築にもつながる重要な要素ですので、正確かつ適切な手続きを心掛けて行ってください。


